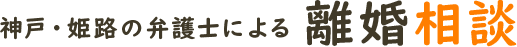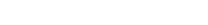親権とは、父母が、未成年の子について一人前の社会人となるよう監護教育し、子の財産を管理し、または養育することを内容とする親の権利義務の総称といわれています。親権には、権利だけなく義務を伴うという要素があります。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚だけを行い、子の親権者を決定・指定することを後ですることはできません。これは、離婚する場合には、父母どちらかの単独親権としなければならないためです。
親権者をどちらにするかについては、基本的には離婚の際に夫婦間で話し合って決めることになります。しかしながら、夫婦間での話し合いで決めることができないときは、協議離婚の届出ができませんので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
ここで大切な事は、子どもの生活・福祉を考えてどちらが親権者となるか決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを双方とも念頭に置く必要があります。
調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、次のようなものがあります。
乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる→基本的には母親が親権者となる
現実に子を養育監護しているものを優先する
15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である→子どもの意思・希望が尊重される傾向にある
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため
→子によって別々の親権者が定められることは基本的にはない
意欲や能力、経済力等があるか
などがあります。
離婚後も子どもについて夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 基本的には子が数人いてもすべての子について同じ親(夫又は妻)が親権者となることになりますが、例外的に夫と妻に親権者を分けることもあります。
親権者を変更することは一般的には非常に難しいものです。
親権者の変更には家庭裁判所の審判が必要であり、家庭裁判所が親権者を変更するのに十分な理由があると認めなければ、親権者を変更することはできないのです。
ですから、離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者を変更できなくなるおそれがあります。ですから離婚届に安易に親権者を記入して提出しないように注意をすることが必要です。

離婚問題を解決するには,離婚条件について,当事者で調整をする必要があります。例えば,子どもがいる夫婦においては,①離婚後の親権者をどちらにするのか,②養育費をいくらにするか,③面会交流をどのようにして行っていくか,というような問題があります。また,金銭的な問題として,④夫婦の共有財産をどのように分けるのか,⑤精神的な苦痛に対して慰謝料が発生するのか,⑥離婚成立までの生活費(婚姻費用)はどちらがどのようにして負担するか,⑦年金分割を行うか,など,決めなくてはならない事柄が多くあります。 これらについて正しい知識がなければ,例えば,相手の言うままに金銭的に不利な条件で離婚に応じてしまって,離婚後に後悔してしまう事態となるかもしれません。弁護士に相談をしていただくことで,どのような離婚条件が適切であるかということを知ることができ,相手と適切な条件交渉をすることが可能になります。離婚の際に決めた条件については,後で変更することが困難ですので,大きな損をすることのないよう,予め弁護士の助言を求めておくことが重要です。

離婚の話し合いは互いの感情がぶつかり合う場面でもあるため,当事者間で解決をすることが難しいケースも多いです。相手と冷静に話ができないということが原因で,離婚協議が膠着してしまうこともしばしばあります。 そのような場合に,第三者を介入させることで離婚条件について冷静に話し合いをすることができ,双方が合意できる妥協点を見つけることも可能となります。例えば,妻に対して高圧的な態度で接してくる夫でも,弁護士を間に入れることで態度が軟化し,話し合いに応じてくることも多くみられます。 当事者間での話し合いができない,切り出すことすら躊躇されるという場合には,まずは一度,弁護士に相談されることをおすすめします。

忙しい方や,ご自身で対応することが難しい方の場合,弁護士に依頼すれば,離婚問題に関するすべての交渉・手続きを弁護士に任せることができます。例えば,離婚協議書を作成するだけだからと言って司法書士に依頼しても,その後,相手との話し合いがこじれてしまった場合には離婚調停や訴訟手続を行わなければなりませんが,それらの手続を代理して行えるのは弁護士だけなので,改めて弁護士に手続を依頼しなければなりません。 また,離婚時に決まった条件(養育費の支払いや面会交流の実現など)がきちんと履行されない場合でも,弁護士に依頼をいただければ,強制執行を行うことも可能です。 このように,離婚協議開始から離婚後のトラブルまでの総合的な問題解決を行うためにも,弁護士に相談されることは非常に有効です。司法書士や行政書士の方が,費用が安いというイメージがあるかもしれませんが,弁護士に依頼する場合とさほど費用が変わらないこともありますし,トラブルとなった後に対応しきれなくなり,改めて弁護士に依頼しなければならなくなれば,結局費用がかさんでしまいます。このため最初から弁護士に依頼するということは十分にメリットがあります。
離婚をするにあたり、互いに親権を譲らないときは、親権と監護権をわけることも選択肢のひとつでしょう。 但し、離婚届をご覧になられればおわかりのとおり、親権者を記載する欄はありますが、監護権者を記載する欄はありません。 そこで、親権と監護権をわける場合、離婚協議書に記載しておく必要があります。できれば真実性を担保するためにも、公正証書の形式で作成しておくことをお勧めします。
親権者にならなかった親が子どもの氏について制約を加えることはできません。氏は当事者で自由に決められることではなく、社会的に個人識別、家族識別をする重要な要素だからです。したがって、ご質問のような約束をしたとしても、そのような約束は無効です。 ただし、子の氏を親権者ではない親の氏にする方法がないわけではありません。具体的には、①子の氏の変更手続を放置する、②子の成人後、1年以内に元の氏へ変更する(民法791条4項)等の方法があります。 いずれにしても、子どもにとって何が一番よいのかという観点から対応されることが望ましいでしょう。
子どもは扶養権利者として、親に扶養を請求する権利があります。この子どもの扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません(民法881条)。 仮に養育費を請求しないと約束しても、その内容は子の福祉を害するものであり、子にとって甚だしく不利益なものといわざるを得ません。 あらためて、あなたは元夫に対し養育費を請求することができます。
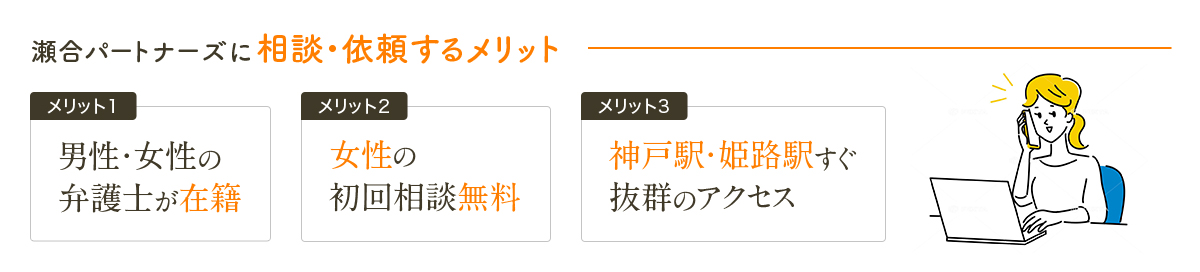
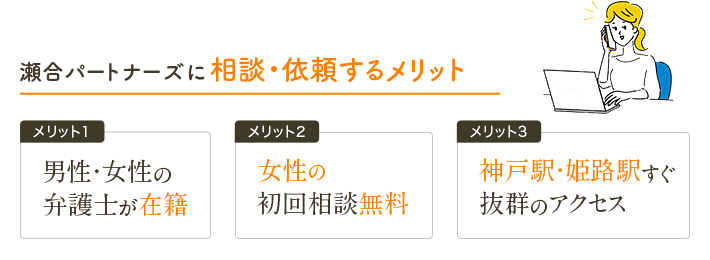
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属
| 所在地 | 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通 2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階 |
|---|---|
| TEL | 078-382-3531 |
| FAX | 078-382-3530 |
| 受付時間 | 平日9時00分~20時00分 |
| 最寄駅 | JR神戸駅、高速神戸駅 |
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属
| 所在地 | 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73 姫路ターミナルスクエア6階 |
|---|---|
| TEL | 079-226-8515 |
| FAX | 079-226-8516 |
| 受付時間 | 平日9時00分~20時00分 |
| 最寄駅 | JR姫路駅 |