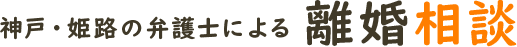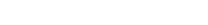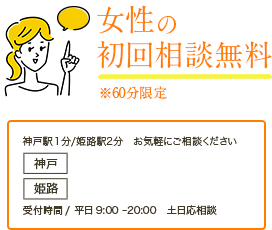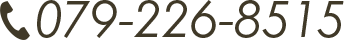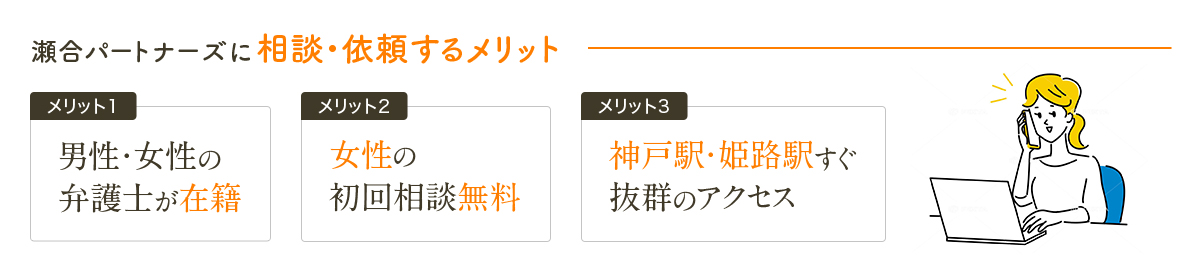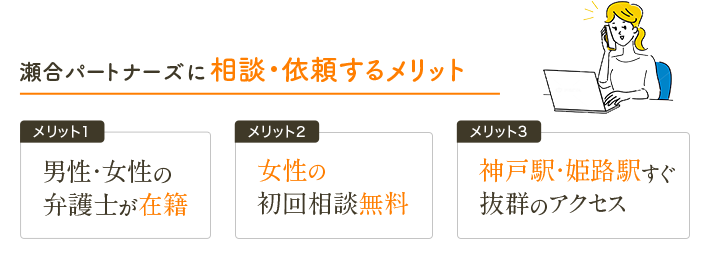法定養育費が請求できるようになります
目次
養育費の取り決めをしていなくても法定養育費が請求できるように

子どもの養育費の取り決めをすることなく協議離婚をしたというケースは決して珍しくありません。
この場合、離婚後に、別居親に対して養育費の請求をすることができます。
ですが、別居親が養育費の支払いに応じない場合は、調停や審判を行って養育費の支払いを求め、調停調書や審判書を得た上で、別居親の給料を差し押さえるなどの手続きが必要となりました。
これらの手続を行うことは非常に手間と時間がかかるため、養育費の請求を断念する原因の一つとなっていました。
今回の民法の改正で「法定養育費」という制度が新しく作られ、今後養育費の支払いが受けやすくなることが期待されています。
法定養育費とは

法定養育費とは、養育費の取り決めをせずに協議離婚をした場合でも、法令で定めた子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用を請求できるものです。
現時点(2025年9月現在)では、法定養育費は月額2万円とする法務省の省令案が発表されています。
これは父母の個々の事情にかかわらず一律に支払いが義務付けられるという法定養育費の性質や、「子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用」という点から、比較的少額とされているようです。
しかしながら、法定養育費は合意ができるまでのあくまでも暫定的な養育費という位置づけとなりますので、その後、父母の具体的な収入状況に応じた妥当な養育費の金額を決めることも可能です。
養育費に優先権がついた
また、今回の民法改正で、養育費には「一般先取特権」と呼ばれる優先権が付けられることになりました。この優先権により、これまでのように公正証書や調停調書、審判書などがなくても、また養育費の取り決めがなくても、法定養育費について、別居親の給料の差押えなどができるようになります。
法定養育費が請求できる要件
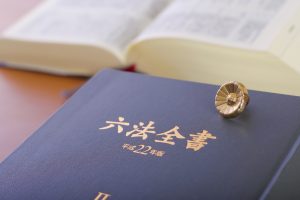
法定養育費を請求するための要件は、次のとおりです。
①「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合」
養育費についての協議や取り決めができなかった理由は問われません。
②「離婚のときから引き続き子の監護を主として行うもの」
法定養育費の請求ができる物は、実際に子と同居するなどして子の養育を主に担当する父母のどちらが請求することができます。
改正法施行前に離婚した場合
法定養育費の規定は、改正法施行前に離婚したケースには適用されません。
このため改正法施行にすでに離婚している場合は、法定養育費を請求することはできません。この場合は、従前どおり、協議によって取り決めを行ったり、家庭裁判所での調停や審判の手続きを行う必要があります。
いつから請求できるのか
改正法が施行されれば、法定養育費の請求ができるのは、離婚の日からとなります(改正後民法766条の3第1項)。
支払義務を負う父母は、毎月末にその月の分の法定養育費を支払う必要があります。
いつまで請求できるか

法定養育費の発生の終期は、次のとおりです。
① 父母が養育費の取り決めをしたとき
② 家庭裁判所における養育費の審判が確定したとき
③ 子どもが18歳に達したとき
法定養育費の減免について
別居親が生活保護を受給しているなどで法定養育費の支払いができないような場合は、法定養育費の全部または一部の支払いを拒むことができます。
この場合は、支払能力がないことや支払いにより生活が著しく窮迫することについて証明することが必要となります。
養育費を諦めないで

今回の改正法により、法定養育費制度が認められたことから、養育費の取り決めがなくても給料の差押えなどができるようになり、従前に比べて養育費の回収がしやすくなったと言えます。
子どもの養育費を負担することは親として当然の義務です。このため、今まで養育費の回収を諦めていた人も、今後は諦めずに少しでも回収できるようになれば良いと思います。
(参考)法務省:父母の離婚後の子の養育費に関するルールが改正されました。
関連記事
・よくあるご相談(目次)へ
・離婚後の共同親権について
・離婚後に単独親権から共同親権へ変更できるか
・養育費未払いに悩む方へ。弁護士が解決策を詳しく解説