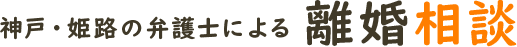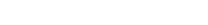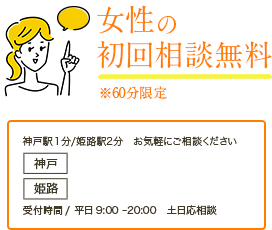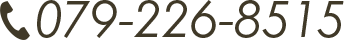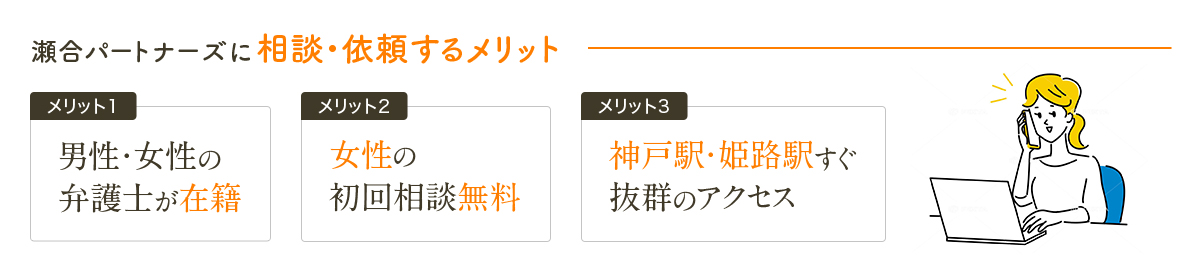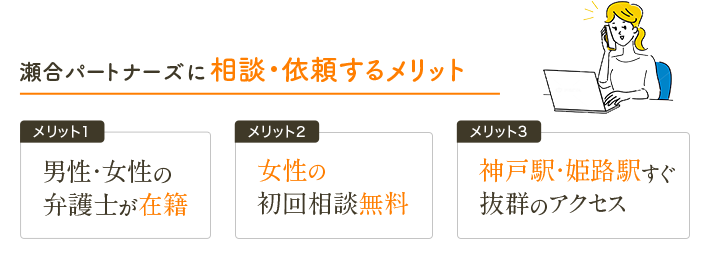財産分与における時効(除斥期間)
離婚における財産分与とは

離婚の際、相手に対して財産分与を求めることができる、というのは多くの方がご存知だと思います。財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきた財産を公平に分けるという考え方に基づいて行われるものですが、実際に財産分与を行う際には、紛争になりやすい部分でもあります。
財産分与においては、どちら名義の財産であるか、どちらの方が収入が多いか、といった事情にかかわらず、婚姻期間中に得た財産は、原則として夫婦の協力によって得られたものとして扱われ、分与の対象となります。具体的に言うと、預貯一方で、結婚前から持っていた財産や、親から相続した財産など、明らかに個人のものと評価できる財産は、「特有財産」として分与の対象から外れます。金、不動産、車、家具、さらには退職金や保険の一部などが対象になります。
財産分与の方法
財産分与にあたっては、基本的には、離婚時に存在する財産から特有財産を除外し、それ以外を共有財産として互いに公平に分けることとなります。
ただし、実際に分与を行う場合には、現金や預金だけでなく、不動産の評価やローンの取り扱い、退職金をどのように評価すべきかなども考慮しなければなりませんので、預金や現金以外の財産がある場合には、一度専門家に相談をした方が良いでしょう。
財産分与の3つの種類
財産分与には大きく3つの種類があるとされています。
まずは、財産を公平に分けるという「清算的財産分与」であり、これが財産分与の中心となります。
次に、離婚後に一方が経済的に困窮するおそれがある場合に、生活を支える「扶養的財産分与」が行われることがあります。
そして、一方配偶者に不貞など婚姻破綻への責任がある場合に、他方配偶者に対する慰謝として行われる「慰謝料的財産分与」があります。扶養的財産分与と慰謝料的財産分与は全ての場合において生じるものではありませんが、該当しそうな事情がある場合には、請求を検討した方が良いでしょう。
財産分与の「時効」

財産分与は、離婚後の生活基盤を築くという意味でも重要であり、また、その請求は権利として認められています。しかし、財産分与の請求には期限があり、離婚が成立してから2年以内に請求しなければなりません。それを過ぎると、原則として請求できなくなりますので、ご注意ください。
ここで注意が必要なのは、この「2年」という期間は、いわゆる「時効」ではなく、「除斥期間」と呼ばれる性質のものだという点です。「時効」という言葉は一般にも馴染みがあるかと思いますが、「除斥期間」という言葉は初めて耳にする方も多いかもしれません。除斥期間は、時効とは少し違ったより厳しいルールといえます。
「時効」であれば、たとえば相手が権利を認めていたり、裁判などで権利行使をしていた場合には、時効が中断されたり、あるいは一定の事情によってその進行が止まることもあります。しかし「除斥期間」はそうした融通が一切利きません。どんな理由があったとしても、2年が経過すれば、その権利は法律上当然に消えることとなります。
たとえば、離婚時に相手が「財産分与は後で話し合おう」と言っていたとしても、実際に請求せずに2年が過ぎてしまえば、もう法的には請求できなくなってしまいます。また、ご病気で手続きができなかったとか、海外に住んでいて連絡が取れなかったといった事情があったとしても、例外にはなりません。除斥期間とは、時間の経過によって当然に権利を失う、非常に強い効果を持つものといえるでしょう。
このような期間制限があるため、離婚をされた際には、財産分与の話し合いを後回しにせず、なるべく早い段階で進めておくことが大切です。もし話し合いがうまくいかないようであれば、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることをお勧めします。除斥期間経過前に調停を申し立てることで、正式に請求の意思を示し、権利が行使されたこととなりますので、調停や審判の成立自体が期間経過後になったとしても、財産分与を受けられることになります。
民法改正による除斥期間の延長
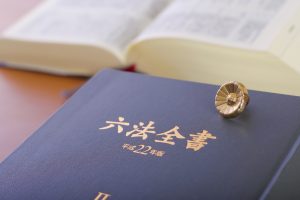
2年間の除斥期間について説明しましたが、今後、法改正により、除斥期間は現行の2年から5年に延長されることが予定されています。
これまでの2年間という除斥期間では、たとえば、離婚時に感情的な対立が激しくて話し合いができなかったり、相手の協力が得られず財産の全容を把握できなかったりという場合には、状況が改善するより先に期間が経過してしまっていました。そして、2年が過ぎてしまうと、それだけで権利が消滅してしまうのです。
そこで、改正法では、この請求期間が5年間に変更されます。この改正によって、離婚後ある程度の冷却期間をおいた上、落ち着いて財産分与の話し合いや請求ができるようになることが期待できます。実際、財産の整理には時間がかかるケースも多く、現実に即した前向きな改正だといえるでしょう。
もっとも、注意していただきたいのは、この改正が実際に適用されるのは施行日以降の離婚に限られる見込みである点です。つまり、それ以前に離婚された方については、今まで通り「2年間の除斥期間」が適用される可能性が高いということになります。したがって、すでに離婚されている方や、現在協議中で離婚が間近に控えているようなケースでは、改正を待つのではなく、現行法のもとで速やかに対応を進める必要があります。
現在は、法改正に伴う過渡期であり、より丁寧な対応が必要になる場面だといえるでしょう。もし、改正によってどのような影響があるのかご心配でしたら、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
関連記事
・よくあるご相談(目次)
・財産分与
・不動産の財産分与
・住宅ローンと財産分与
・自宅の財産分与と建物明渡請求・共有物分割請求
・借金は財産分与の対象になりますか?
・配偶者が取得した交通事故による損害保険金は、財産分与の対象となる?
・学資保険は財産分与しなければならいのでしょうか?
・破産した相手方に財産分与と養育費の支払いを請求できますか?
・離婚時に財産分与をしなくてもいい場合