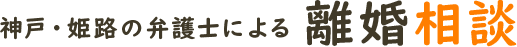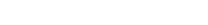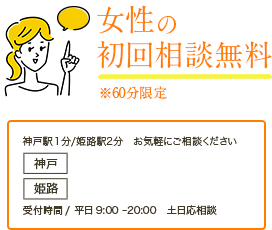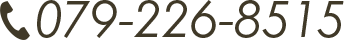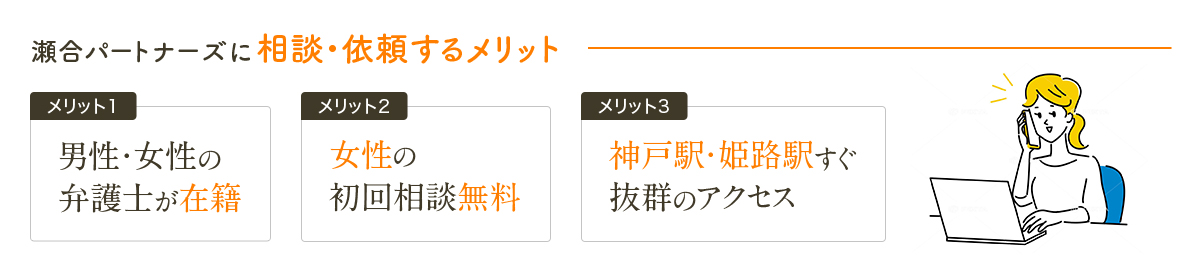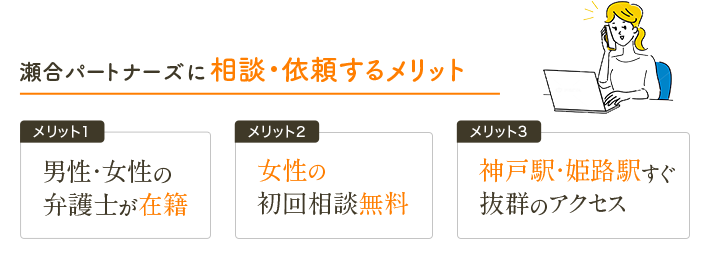離婚時に財産分与をしなくてもいい場合
目次
財産分与の原則ルールと例外

財産分与とは、離婚の際に、夫婦が協働して得た財産について、夫婦の一方が他方にあるいは相互に分与するという制度です(民法768条)。この財産分与における清算の割合については、共稼ぎの夫婦、妻が専業主婦の夫婦いずれの場合であっても、原則として割合を2分の1とするいわゆる2分の1ルールが実務の扱いです。
財産分与にあたっては2分の1ルールが原則にはなりますが、財産の増加が分与義務者の特別の才能や特有の事情の寄与が著しく大きい場合においては修正されます。裁判例の中には、開業当時はみるべき資産がなかった医師の夫が、次第に盛業になり、高額の資産形成がされた事案において、夫が多額の資産を有するに至ったのは、妻の努力があったこともさることながら、夫の医師ないし病院経営者としての手腕、能力に負うところが大きいものと認められるなどの理由から、財産分与の基準を2分の1とすることは妥当でないと判示したものも見られます(福岡高判昭和44年12月24日判時595号69頁)。
財産分与をする必要がない場合
① 財産を夫婦の協働で得たものではないとき

以上のことを前提にすると、まず財産分与の必要がない場合としては、その財産が夫婦の協働で得たものではない場合が考えられます。
例えば、婚姻前に取得した財産や、婚姻中に取得した財産であっても、それが夫婦の一方が親から贈与を受けたものであれば、その財産は夫婦が協働して取得した財産とはいえないため、このような財産は財産分与の対象とはなりません。
② 婚姻の届出前に別段の合意がある場合

婚姻届を提出する前に夫婦財産契約を締結していれば、夫婦間での財産の帰属は、その契約によることとなります(民法755条、民法758条1項)。このため、夫婦財産契約をしていれば、仮にその財産が夫婦が婚姻中に協働して取得した財産であった場合でも、契約によりその扱いを変更することで、財産分与の対象から外すことが可能となります。
もっとも、このような夫婦財産契約は利用されていない状況にあるのが実情です。夫婦財産契約は、婚姻の届出前にすることが必要なのですが(民法755条参照)、まさに今から結婚をしようとする場面で、離婚を前提とするような夫婦財産契約を行いにくいという背景があると思われます。
③ 離婚時に財産分与を放棄した場合

離婚時に財産分与を請求する権利のある人がその権利を放棄すれば、財産分与をする必要がなくなります。この場合には、あとでその合意の有効性が問題とならないように、その合意内容を書面などに残しておくのが望ましいでしょう。
④ 期間が経過した場合

財産分与請求には期間制限があり、離婚の時から2年を経過すると請求はできなくなります(民法768条2項)。なお、この規定は令和6年民法改正により期間が延長されることが決まっており、従来の2年間から5年間に延長されます。この改正法は、2026年5月までには施行されることになっています(2025年5月現在では施行日は未定)。
まとめ
財産分与は、原則として2分の1の割合で行われることになりますが、上記のような場合は財産分与をする必要がない場合もあります。財産分与をしなければならないか判断がつかない場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。