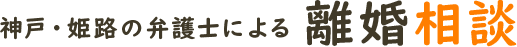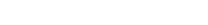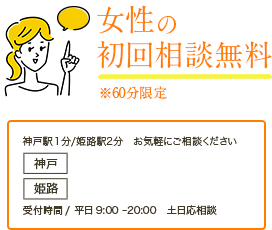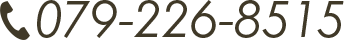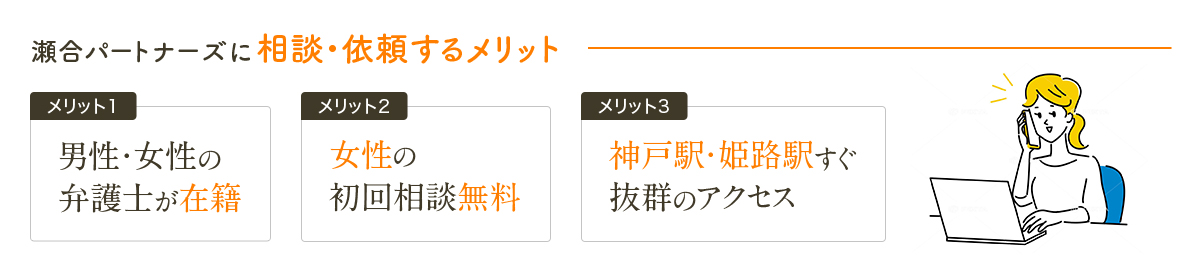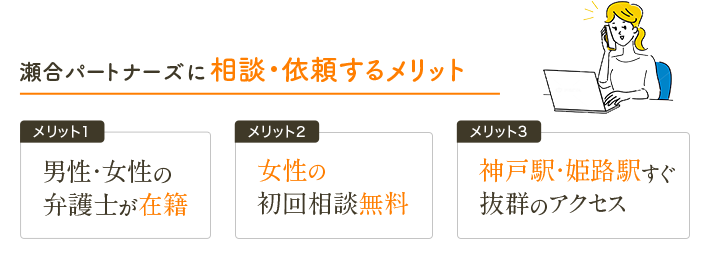特有財産とは?財産分与の対象から外す方法
目次
第1 初めに
「特有財産」という言葉をご存知でしょうか。特有財産とは、簡単に言うと、離婚時の財産分与において、分与対象にならない財産のことをいいます。
ある財産が特有財産に当たるかどうかによって、財産分与の金額は大きく変わる可能性があるため、非常に重要な問題です。
そこで本記事では、特有財産とは何なのか具体例を交えながらご説明した上で、争いになりやすいケースや特有財産であることの証明方法について詳しく解説していきます。
第2 特有財産とは
1 特有財産の考え方
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を公平に分ける手続であり、財産分与の対象となる財産を「共有財産」といいます。
例えば、夫婦が婚姻後に購入した不動産は、たとえ名義が夫婦のどちらか一方だけであったとしても、実質的には夫婦が協力して築いた財産といえるため、財産分与の対象となります。
他方、夫婦の一方が有する財産の中でも、配偶者の寄与・貢献など一切なく個人で築きあげた財産もあるでしょう。これを「特有財産」というところ、特有財産は、夫婦で協力して築いたものではありません。そのため、財産分与の対象から外されるのです。
2 具体例
一般的に特有財産として認められているのは、以下の通りです。
①夫婦の一方が婚姻前に取得した財産
例:婚姻前に貯めていた預貯金
②夫婦の一方が婚姻後に相続や贈与によって取得した財産
例:婚姻後に親からの相続で取得した不動産
③社会通念上、一方の専有品といえる財産
例:衣類、宝飾品
財産分与は、夫婦が有している財産の全てを分けるという手続ではないため、誤解しないようにしましょう。
第3 財産分与の対象から外すためには
1 争いになりやすいケース
財産分与の対象から外すためには、特有財産の範囲・額を特定する必要があります。
婚姻後に相続で不動産を取得したという場合であれば、その特定は容易でしょう。もっとも、1つの財産の中でも共有財産と特有財産が混在しているケースがあります。例えば、以下のようなケースです。
①婚姻前に貯めていた預貯金口座を婚姻後も使っているケース
既に述べた通り、婚姻前に貯めていた預貯金は、配偶者の寄与なく築いた財産であるため、特有財産として財産分与の対象から外れるのが原則です。
もっとも、その口座を婚姻後も利用する場合、婚姻後の入金は共有財産となるため、1つの口座に特有財産と共有財産が混在することになります。そして、一度混在してしまうと、どこまでが特有財産で、どこからが共有財産なのか切り分けるのが難しく、その範囲をめぐって争いが生じやすくなります。
②婚姻後に取得した不動産の頭金を特有財産から支払っていたケース
不動産の取得にあたって、婚姻前に貯めていた預貯金や親から贈与を受けた金員を頭金に充てるという場面はよくみられます。この場合、不動産の価値のうち、頭金部分は特有財産として、財産分与の対象から外れることになります。
もっとも、この場合でも、頭金が特有財産から支払われたことを裏付ける証拠の有無や特有財産部分の計算方法をめぐって争いになることが多々あります。
2 特有財産性は自ら立証する必要あり
夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、共有財産であると推定されます(民法762条2項)。
そのため、ある財産の特有財産性が争いとなった場合には、特有財産性を主張する側がその範囲や金額を証拠によって証明する必要があります。
3 具体的な立証方法
では、特有財産性の立証とはどのようにして行えばよいのでしょうか。上記2つのケースを例に解説していきます。
⑴ ①の場合
まず、婚姻前に貯めていた預貯金額を立証するため、婚姻時点での口座残高がわかる資料(通帳の記載、残高証明書)が最低限必要です。
その上で、財産分与において特有財産として扱われるためには、基準日(≒別居日)時点でも、その金額が残っているということを立証しなければなりません。そのため、婚姻時から別居時までの口座の動きがわかる資料(通帳の記載、取引履歴)も必要になります。
この点、定期預金など基本的に動きがない口座であれば、上記資料を用いることで、特有財産の範囲・額は容易に立証できるでしょう。
他方、普通預金など婚姻後も頻繁に入出金が繰り返される口座の場合、話は複雑になります。この場合でも、婚姻してから別居するまで、口座残高が増え続けていたということであれば、婚姻時の残高が別居日時点でもそのまま残っていたとして、婚姻時の残高=特有財産の金額と捉えることが可能でしょう。
もっとも、そうではなく、婚姻後に口座残高が増減を繰り返していたような場合には、特有財産と共有財産が渾然一体となってしまうため、その切り分けは非常に難しくなります。そのため、このような場合、婚姻時の残高が特有財産として別居日時点でもそのまま残っているという主張は、認められない可能性が高いでしょう。
⑵ ②の場合
まず、頭金の額や不動産の購入価格に占める頭金の割合を立証するため、不動産の登記事項証明書や売買契約書が必要となります。
その上で、頭金の領収書や預貯金の取引履歴、贈与税の申告書等があれば、当該頭金が特有財産から支払われたということも立証可能でしょう。
ただ、不動産の価値は、時の経過と共に変動していくのが通常です。このとき、頭金が特有財産から支払われたことは立証できたとして、特有財産部分の金額はどのように計算すればよいのでしょうか。
考え方は複数ありますが、一般的なのは、不動産の購入価格に占める特有財産部分(=頭金部分)の割合を算定し、そこに不動産の時価を乗じるというやり方です。計算式は以下の通りです。
不動産の時価×(特有財産部分÷不動産の購入価格)
例えば、ある夫婦が婚姻後、自宅不動産を5000万円で購入し(現在価値4000万円)、そのうち頭金800万円を夫が婚姻前に貯めていた預貯金から支払っていた場合、特有財産の金額は、以下のようになります。
4000万円×(800万円÷5000万円)=640万円
共有財産が当該不動産のみであった場合、各自の取り分は以下の通りとなります。
夫:640万円+({4000万円-640万円}×2分の1)=2320万円
妻:(4000万円-640万円×2分の1)=1680万円
第4 終わりに
冒頭でも述べた通り、ある財産が特有財産に当たるかどうかは、当事者にとって非常に重要な問題です。
もっとも、1つの財産の中に特有財産と共有財産が混在している場合も多く、特有財産性の立証も上記の通り決して容易ではありません。そのため、争いになった場合には、1人で解決するのは難しく、専門的知識を持った弁護士の関与が必須といえるでしょう。
本記事の内容についてお悩みの方は、離婚分野に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。