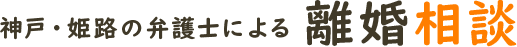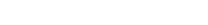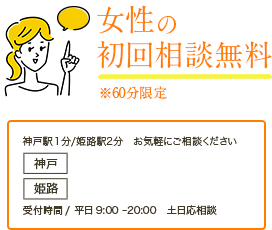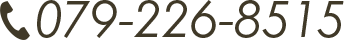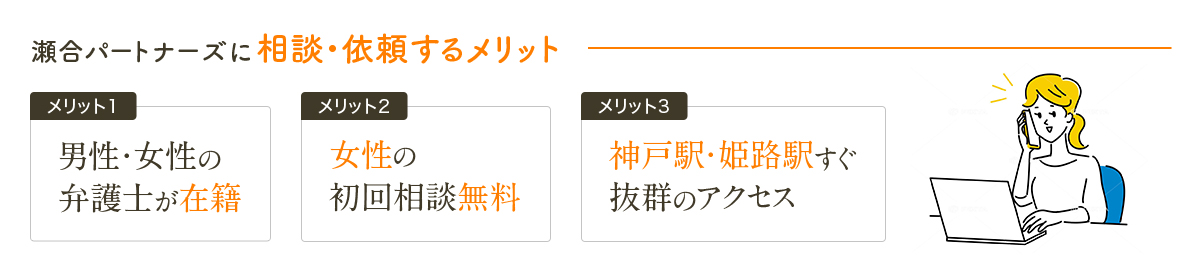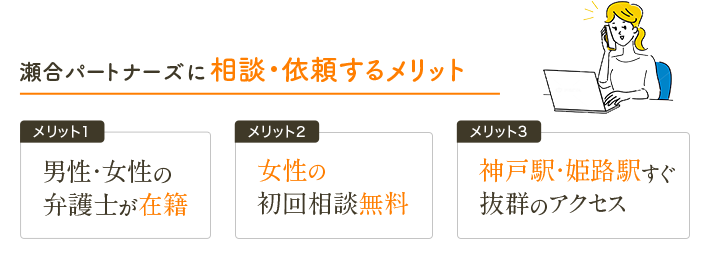医師の離婚問題
目次
医師の離婚問題の特徴

財産分与が高額になる傾向がある
厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査によると、令和5年の医師の平均年収は1436.5万円、開業医の平均年収は約2500万円というデータもあります。このため、医師は一般的に高所得者であると言えます。
このため、高額所得者として財産分与の金額が高くなる傾向があります(参考:高額所得者の離婚についてて)
養育費の金額が高額になる可能性がある
医師の場合、自分の子どもも医学部に進学させようと考えている家庭も少なくないようです。このため、子どもが小さい頃から教育費をかけ、子どもを私立の学校に通わせることも多いようです。また、子どもが医学部に進学した場合、6年間大学に通わせ、その学費が非常に高額になるケースもあります。
私立の学校に通わせたり、医学部に通わせることを夫婦が納得していた場合は、高額な学費のため、養育費の金額が一般的なケースよりも上乗せされる可能性があります。
不貞行為の慰謝料が高額になる傾向がある
医師の場合、職場に異性が多く、不規則勤務や出張などで外泊等が不自然ではないという環境もあって、不貞行為を行うことも珍しいことではないようです。中には夫婦ともに医師で、夫婦ともに不貞行為をしているというようなケースもあるようです。
このため、不貞行為により離婚となる場合は慰謝料を支払うことになりますが、高収入であることも慰謝料額を決める要素の一つとなりますので、慰謝料が高額になる可能性があります。
財産分与が複雑となる傾向がある
特に開業医や医療法人などの場合、財産分与が複雑になる傾向があります。
医療法人であれば、法人の財産は財産分与の対象とはなりませんが、個人の開業医の場合は、個人の財産として事業用の資産も財産分与の対象となる可能性があります。
このため、一般的なケースと比べて財産分与が複雑となる傾向があります。
財産分与で注意すること

2分の1ルールが修正されることもある
一般的な夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的には2分の1ずつなのですが、夫婦の一方のみが医師である場合は、その割合が修正されることがあります。
古い裁判例にはなりますが、福岡高裁昭和44年12月24日判決の事案では、「夫が医者として病院を開業し、1969年当時の年収が1億円を超え、かつ1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、妻に2000万円の財産分与しか認めませんでした。
この裁判例な特殊なケースと言えますが、財産分与の金額が多いような場合は、2分の1ルールの修正を検討しても良いかもしれません。
医療法人の場合
医療法人の場合、法人と個人は別人格であるため、医療法人の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。
ただし、理事長個人が所有する不動産や金銭を医療法人に貸し付けていたり、医療法人の出資持分を有していたりすることがあります。この場合は、所有不動産や貸付金、出資持分は医師個人の財産として財産分与の対象になる可能性があります。
出資持分が財産分与の対象となる場合は、その評価額をめぐって争いになることもあります。医療法人は一般的に高額な医療機器を保有していることも多く、出資持分の評価額が高額になる場合もあります。
なお、親が経営していた医療法人を相続した場合などは、出資持分は特有財産として財産分与の対象とはならない場合があります。
保険について
医師の方は病気や怪我に対する危機意識が高いためか、生命保険などの保険を契約していることも多いです。一般の方よりも高額な保険に加入しているケースもあるようです。このため、財産分与の計算を行う場合には、保険をもれなく調査することが必要です。
その他の財産について
医師は高額所得者が多いため、高級車を有していたり、高額な貴金属、腕時計、絵画や骨とう品を収集している場合もあるようです。このような動産(物)でも、評価がつくものは財産分与の対象になる可能性があります。
配偶者が役員になっている場合
配偶者が医療関連会社の役員になっているというケースもあります。その場合、離婚するからと言って当然に役員を退任することになる訳ではありません。このため、辞任届を提出してもらうなど、通常と同じ手続を踏んで退任登記を行う必要があります。
また、配偶者を個人医院や医療法人の従業員として雇用しているケースもあるかと思います。
その場合も、離婚を理由として解雇することはできませんので、一般の従業員と同様の退職手続を踏む必要があります。
離婚後に引き続き雇用されることを望まないケースが多いと思います。ですから、離婚をする際に併せて退職の意向を確認し、退職届を提出してもらうなどして退職手続をきちんと行っておくことが必要です。