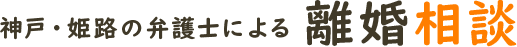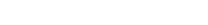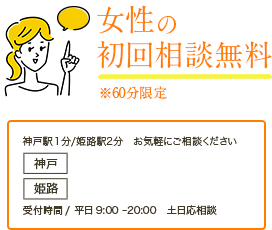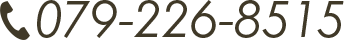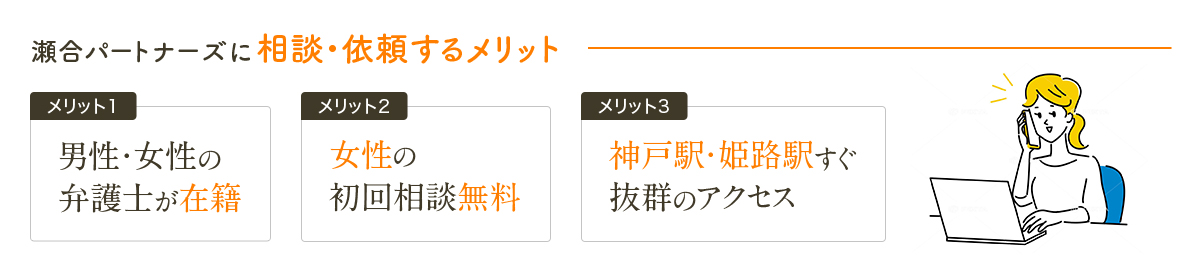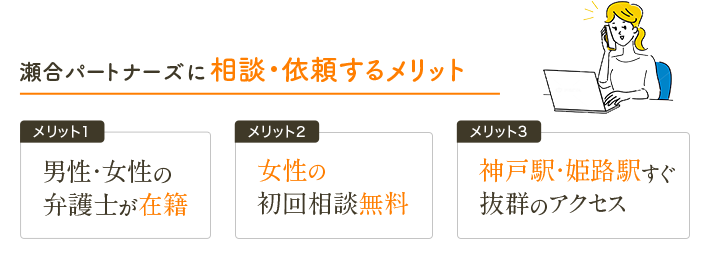調停離婚について
目次
調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦間で話し合って協議離婚をすることができない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、その調停の話し合いにより離婚することを言います。
離婚の話し合いがうまくいかない場合でも、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、まずは調停を行う必要があります(調停前置主義)。
調停というと、裁判と同じようなイメージを持たれる方もいらっしゃると思います。
しかし、調停は裁判のように裁判官が一方的に結論を決めるのではなく、調停委員を間に入れ、相手方と話し合いにより解決を目指すものです。
ですから、調停で相手方が全く話し合いに応じなかったり、離婚条件について合意ができなかった場合は、調停離婚をすることができません。
ただ、当事者だけで話し合いをするのとは異なり、調停委員が間に入って話をしてくれますので、当事者同士で話し合いをするよりも比較的冷静な話し合いをすることができます。
調停離婚の手順
離婚調停の流れは次のようになります。
| ① 家庭裁判所への調停の申立て ② 家庭裁判所から第1回目の調停期日への呼出状が届く ③ 第1回目調停(申立てから1か月以上先のことが多い) ④ 第2回目調停~最終調停 ⑤ 調停調書の作成 |
家庭裁判所への調停の申立て
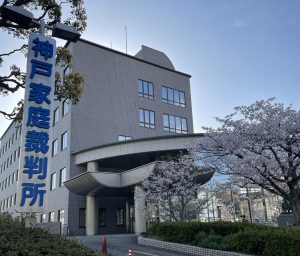
離婚調停の申立ては、夫婦のどちらか一方が、管轄の家庭裁判所に夫婦関係事件調停申立書を提出して申立てを行います。
調停申立書の書式は、裁判所に備え付けられている他、裁判所のホームページでも公開されています。
申立書の書式に必要事項を記載し、所定の手数料を添えて裁判所に提出して申立てを行います。
調停申立書には、離婚を求める理由、親権者、養育費、財産分与、慰謝料の金額等についての記入欄がありますので、自分の主張を記入します。
申立書に記載する金額について見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談しておくことも有効です。
呼出状が届く
調停申立書が裁判所で受理されると、家庭裁判所から呼出状が当事者双方に郵送されます。
呼出状には、第1回目の調停期日の日時が記載されていますので、指定された日時に家庭裁判所に出頭します。
調停期日にどうしても出頭できない場合は、期日を変更してもらうこと等も可能です。
呼出状に記載された日時の都合が悪い場合は、家庭裁判所にその旨を連絡しておきましょう。
無断欠席が続くと調停が不成立となり、離婚訴訟を提起される可能性があります。
第1回目調停

調停には本人が出席する
調停には当事者本人が出席することが必要です。
遠方の場合は、電話会議やWEB会議によって調停を進められるところもあります。
弁護士を依頼する場合でも、可能であれば弁護士と一緒に調停に出席する方が良いでしょう。
どうしても出席できない場合は、弁護士に任せることも可能です。
もっとも、当事者が不在であるあと調停での話し合いがなかなか進まないこともあります。
このため、やむを得ない事情がない限り調停には出席することをおすすめします。
どんな服装で行けばいいのか
調停に出席する場合の服装は特に決まりはありません。
普段着で良いのですが、調停委員に悪い印象を与えないような服装を心掛けるのが良いでしょう。
調停当日の様子
調停当日は、家庭裁判所の調停係で受付を済ませ、指示された待合室で呼び出されるのを待ちます。
待合室は、申立人用の待合室と相手方用の待合室が用意されているので、待合室で相手に鉢合わせることはありません。
調停では2名の調停委員(男女のペアであることが多い)が、当事者の話を交互に聞いてくれます。
調停では、相手と直接話をすることは基本的にはありません。
1回目の調停では、まずは申立人が先に調停室に入室し、調停委員に対して20~30分程度の時間で事情を説明します。
申立人が退室した後に、今度は相手方が入室し、調停委員から申立人の主張を聞いたり、それに対する反論などを主張していきます。
1回の調停にかかる時間は2~3時間程度です。通常1回目の期日で調停が終了することはなく、その後も何回か期日を入れて話し合いを続けて行きます。
1回目の調停の最後に、基本的には当事者双方が同席して、次回の調停期日を決めるとともに、次回期日までに準備する資料等を確認します。
2回目以降の調停
調停はその後も、1か月~1か月半程度の間隔で行われます。
4か月~半年程度で終了する事案が多いですが、対立が激しい場合は1年以上かかるケースもあります。
調停で離婚が成立する際には、原則として当事者本人の出席が必要となります。
調停調書の作成
調停で離婚条件等がまとまると、裁判所において調停調書が作成されます。
調停成立時には、当事者双方とその代理人の弁護士、調停委員、裁判官、書記官が一同に会し、合意した離婚条件について口頭で確認を行います。
そして、この内容が調停調書という書面にまとめられることになります。
調停調書は、裁判所が作成する書類なので、当事者が調停調書に署名押印などをすることはありません。
調停調書には、離婚の合意の他、未成年の子の親権者を誰と定めるのか、養育費・財産分与・慰謝料などの金額や支払い方法、年金分割等、相手方との間で合意した内容のすべてが記載されます。
調停調書が作成された後には、誤記などの場合を除いて、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。
このため、誤解のないよう、裁判官や調停委員からの説明を良く聞き、疑問がある場合は遠慮せずに質問して、十分に納得することが必要です。
離婚届の提出

調停離婚が成立した場合、調停終了から10日以内に市役所や区役所に離婚届を提出する必要があります。離婚届の提出をしないと離婚の手続が完了しませんので、忘れないように提出するようにしましょう。
調停離婚の場合、協議離婚とは異なり、相手方の署名押印が必要ありませんので、当事者の一方が記載するだけで離婚届を提出することができます。また、証人の署名押印も不要です。
子どもの戸籍を移す

離婚後、妻側は、戸籍から離れて新しい戸籍を作る方が多いようです。
妻が子どもの親権者となって離婚により新しい戸籍を作っても、子どもの戸籍が当然に妻の新しい戸籍に入る訳ではありません。
何も手続きをしなければ、子どもは筆頭者である夫の戸籍に入ったままの状態になります。
子どもを妻の新しい戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」を行い、家庭裁判所の許可を得てから、妻の戸籍に入籍する手続が必要となります。
なお、妻が離婚後も婚姻時の姓を名乗り、離婚により子どもの姓が変わらなくても、子を妻の新しい戸籍に入れるには、子の氏の変更許可の申立ての手続が必要となります。
家庭裁判所の許可審判を得たら、家庭裁判所から交付される審判書と戸籍謄本を添えて、役所に入籍届を提出することになります。
関連記事
・調停・訴訟には本人が必ず出席しなければならないか?
・調停を取り下げた場合でも離婚裁判を起こせますか?
・調停で提出した書面や証拠は、訴訟に引き継がれますか?
・よくあるご相談(目次)へ
・解決事例(調停)へ