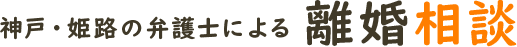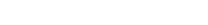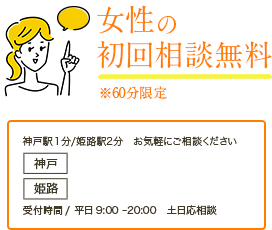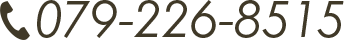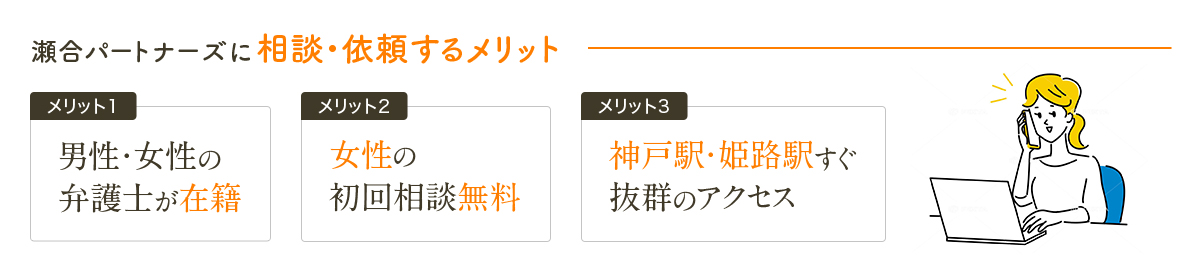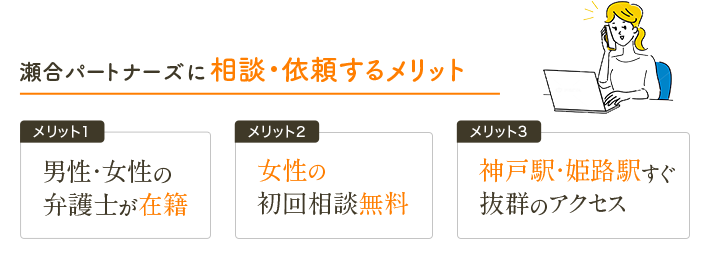子どもの私立学校の学費は婚姻費用算定にあたり考慮されるか?
目次
問題提起
法律上、配偶者は他方の配偶者に対し、また親は子に対し、相手の生活レベルを自分の生活レベルと同等に維持してやらねばなりません。これを「生活保持義務」といいます。この義務に基づき、離婚が成立するまでは婚姻費用を、離婚成立後は養育費を支払う義務が生じ、それぞれ、裁判所が作成した算定表に基づいて金額が決まるのですが、お子様が私立学校に通っている場合、その費用はどのように考慮されるかが問題になります。
事案の概要
本件は、妻が子どもを連れて別居した後、長男が私立中学に進学、その後、同中学の高等部に進学した家族で、妻が夫に対し、婚姻費用の分担を請求した事案です。
夫の収入は1311万円、妻の収入は約360万円で、長男の私立高校の学費は、旅行等積立金などの諸費用を含めて年間で約90万円でした。
本判決
ア 標準的算定方式を使うかどうかについて
本判決は、「婚姻費用の算定方法としては、いわゆる標準的算定方式が合理的な算定方式として実務上定着しているので、まずこれによる試算を行う」としました。
イ 長男が私立高校に通っていることを考慮するかどうかについて
この点、「抗告人(夫を指します。)は同居中に私立中学受験を前提にして長男の家庭学習を指導していたと認められるほか、別居後も、長男が私立中学に在籍していることを前提に、婚姻費用を支払ってきたことが認められる。
また、同中学は中高一貫教育校であるから、中学部に在籍している生徒は、特段の問題がなければ、そのまま高等部に進学する例が多いと考えられる。したがって、中学及び高校を通じて私立学校の学費等を考慮するのが相当である(なお、当事者双方の別居をもって、直ちにこの特段の問題に当たるということはできない。)。」とし、算定表で算出された金額を修正すべきだとしました。
ウ どのように考慮するかについて
「標準的算定方式においては、15歳以上の子の生活費指数を算出するに当たり、学校教育費として、統計資料に基づき、公立高校生の子がいる世帯の年間平均収入864万4154円に対する公立高校の学校教育費相当額33万3844円を要することを前提としている。
そして、抗告人と相手方(妻を指します。)の収入合計額は、上記年間平均収入の2倍弱に上るから、(中略)標準的算定方式によって試算された婚姻費用分担額が抗告人から相手方へ支払われるものとすれば、結果として、上記学校教育費相当額よりも多い額が既に考慮されていることになる。
そこで、既に考慮されている学校教育費を50万円とし、長男の私立高校の学費及び諸費の合計約90万円からこの50万円を差し引くと40万円になるところ、この超過額40万円は、抗告人及び相手方がその生活費の中から捻出すべきものである。
そして、標準的算定方式による婚姻費用分担額が支払われる場合には双方が生活費の原資となしうる金額が同額になることに照らして、上記超過額を抗告人と相手方が2分の1ずつ負担するのが相当である。」
とし、夫は妻に対し、超過額40万円(年間)の2分の1を、標準的算定方式によって得られた金額に上乗せして支払うべきだと判示しました。
この裁判例のポイント

まず、婚姻費用の算定にあたり、子どもが私立学校に通っており、公立より多くの学費がかかることを理由に、算定表で導き出された金額に修正を加えた点が大きいです。ただし、夫が子どもの私立中学進学に反対していなかったことが前提とされており、この点、参考になります。
また、いかに考慮するかについては、算定表に織り込まれている金額を超える部分を超過教育関係費とみなし、これをどう分担させれば夫婦及び親子の生活レベルが同等になるかを細かく判断しています。すなわち、世帯の収入が標準(年間で864万4154円)よりも高い場合、算定表で算出された金額には、すでに、通常(高校生の場合、年間で33万3844円)より高い教育費が織り込まれているから、その金額(本件では50万円としました。)を基準に超過教育関係費を判断し、また、その超過部分の負担を、2分の1ずつ分ければよいとしました。
ですので、たとえば、世帯の収入が標準よりも低ければ、超過教育関係費はより多く見積もられたでしょうし、その超過部分は収入に応じて負担せよ、と判断した可能性も考えられます。
このような観点や判断方法は、私立学校に通われているお子様がいるご家庭で、大いに参考になると思われます。
(大阪高裁平成26年8月27日決定をもとに)